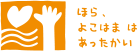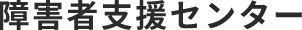横浜市障害者後見的支援制の成り立ちと目的
横浜市障害者後見的支援制度の歩み
横浜市障害者後見的支援制度は、「将来にわたるあんしん施策」の中核的施策の1つとして、平成22年に発足しました。
障害福祉サービスが充実してきた現在でも、地域で暮らす障害のある人やその家族は様々な不安を抱えています。中でも「親亡き後の不安」を抱いている家族は多くいらっしゃいます。
横浜市は「親亡き後も安心して地域生活が送れる仕組みの構築」について、「後見的支援推進プロジェクト」を立ち上げ、検討を進め、必要なことをまとめました。
親亡き後の本人の地域生活を支えるために必要なこと
- 障害者本人を中心に据えた制度設計
障害者本人の人生を、本人が決定する仕掛けを構築することが必要である。 - 生活をコーディネートする機能の中立性の確保
本人の生活をコーディネートする機能は、本人にとって何が一番適しているのかを考えることができる、中立的な立場であってほしい。 - 地域の人が参加する仕組み
成年後見人や、障害福祉関係者だけで本人の地域生活を支えていくことは困難。地域の人が参加する仕組みを考える必要がある。 - 本人の話を聞く人の必要性
親亡き後にも「本人の話を聞く人」の存在が必要である。
これらを踏まえ、具体的な対応策として『横浜市障害者後見的制度』が誕生しました。
平成22年10月から、4区でこの制度は実施され、ました。その後、各区に広がり、平成29年3月には全区での実施となりました。
| 開始時期 | 実施区 |
|---|---|
| 平成22年10月 | 南区 保土ケ谷区 都筑区 栄区 |
| 平成25年3月 | 鶴見区 磯子区 港北区 |
| 平成26年3月 | 西区 旭区 金沢区 緑区 |
| 平成27年3月 | 神奈川区 戸塚区 泉区 |
| 平成28年3月 | 港南区 青葉区 |
| 平成29年3月 | 中区 瀬谷区 |
将来にわたるあんしん施策とは
昭和48年に作られた「在宅心身障害者手当」の質的転換策として、平成21年度から進められてきた障害のある人が地域で安心して暮らすための施策です。
後見的支援推進プロジェクト
当事者2名、当事者の家族2名、支援者3名、弁護士1名から構成され、「親亡き後も安心して地域生活が送れる仕組みの構築」に関する施策の具体化に向け、検討を進めました。
横浜市障害者後見的支援制度検証委員会
平成22年10月の制度開始にあたり、制度運用にかかわる検証のため、「横浜市障害者施策推進協議会(障害者施策の推進について審議するために、横浜市に設置されている審議会)」の部会の一つとして設置されました。
障害児・者やその家族、学識経験者、弁護士、障害者の福祉に関する事業に従事する者等の委員により構成され、制度の理念や趣旨、内容が運用の中で活かされているかを確認すること、また、効果的な運用のための課題整理や手法等を検討することを目的としています。
横浜市障害者後見的支援制度業務運営指針(ガイドライン)
横浜市は、制度が将来にわたり安定的且つ持続可能な制度となるよう、運営上発生している諸課題の解決策等を含むその在り方を検討するため、令和元年度から3年度にかけ、「横浜市障害者後見的支援制度あり方検討会」を開催しました。そこでの検討内容を集約し、改めて、制度の意義や目的等を明確化するために策定したものです。