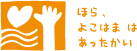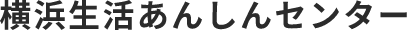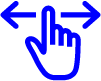法定後見制度
法定後見制度
法定後見制度は 後見・保佐・補助 の3つの類型に分かれます。
- 親族等の申立人から法定後見の開始の審判を申立て、家庭裁判所で適任と思われる成年後見人等が選ばれます。
- 後見・保佐・補助のいずれを申し立てるかは医師の診断書を参考にして決めます。
- 場合によって成年後見人等を監督する監督人が選ばれることがあります。
要件などを整理すると次のようになります。
| 類型 | 後見 | 保佐 | 補助 | |
|---|---|---|---|---|
| 要件 | 判断能力 〈対象者〉 |
判断能力が欠けているのが通常の状態の方。 日常的な買い物もできず、誰かに代わってやってもらう必要がある。 |
判断能力が著しく不十分な方。 日常の買物程度は一人でできるが、不動産売買や金銭の貸し借りなど重要な財産行為は自分でできない。 |
判断能力が不十分な方。 重要な財産行為は自分でできるかもしれないが、できれば誰かに代わってやってもらったほうが良い。 |
| 鑑定の要否(原則) | 必要 | 必要 | 不要 | |
| 開始手続 | 申立人(参考1) | 本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人など、成年後見監督人など、検察官、任意後見受任者、 任意後見人、任意後見監督人、市区町村長 | ||
| 本人の同意 | 不要 | 不要 | 必要 | |
| 同意権・取消権(参考2・3) | 同意の必要な行為 | – | 民法13条1項所定の行為 (具体的には借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為で、ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除く) 家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても範囲を広げることができる。 |
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為(民法13条1項所定の行為の一部) (具体的には、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為で、ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除く。) |
| 取消の可能な行為 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 同上 | 同上 | |
| 代理権(参考3) | 付与の範囲 | 財産に関するすべての法律行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 | |
| 付与の審判 | 不要 | 必要 | 必要 | |
| 本人の同意 | 不要 | 必要 | 必要 | |
| ー般的責務 | 本人の意思の尊重、本人の心身の状態および生活の状況に配慮 | |||
参考1
四親等内の親族図
親族の範囲 六親等内の血族、三親等内の姻族(民法725条)
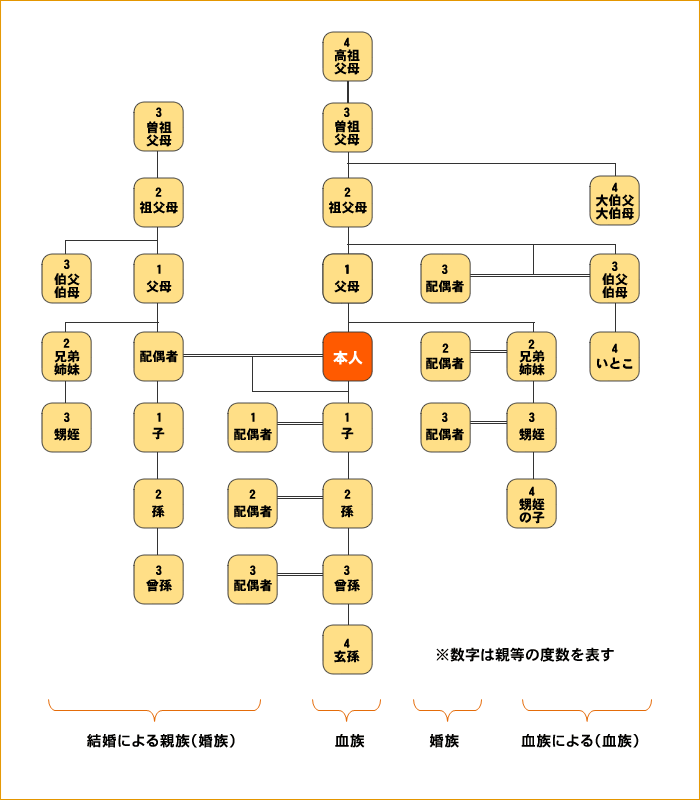
参考2
同意権・取消権の範囲 「民法13条 1項各号所定の行為」
- 元本(例:預金や貸金などの元金)を領収したり、これを利用すること。
- 借財(借金)をしたり他人の保証をすること。
- 不動産その他重要な財産に聞する権利を得たり失ったりする行為をすること。
- 訴訟を行うこと。
- 贈与、和解又は仲裁契約をすること。
- 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
- 贈与若しくは遺言により与えられる財産を拒絶し又は負担のついたこれらを受けとること。
- 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
- 民法602条に規定する期間を超えて賃貸借をすること。
参考3
- 同意権
- 本人が契約など法律行為をするときにそれを承諾する権限
【例】
家のリフォーム契約を本人がする時は保佐人、補助人の承諾が必要。
親が亡くなり、相続をする場合は、保佐人、補助人の承諾が必要。 - 取消権
- 本人が成年後見人等の同意なしに行った法律行為などを取り消す権限
【例】
本人が一人で必要のないリフォーム契約をしてしまった時、成年後見人等の同意なしにした契約は、成年後見人等が取り消すことができます。 - 代理権
- 本人に代わり成年後見人等が、取引や契約など法律行為をする権限
【例】
通帳から本人に代わりお金を引き出すことができます。
本人に代わり、施設入所の契約をすることができます。
法定後見手続きの流れ
- 申立て準備必要書類を揃えたり、成年後見人等の候補者を決めたりします。
(※必要書類参照) - 申立て本人の住所地もしくは居住地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※家庭裁判所に予約が必要 - 審判手続き
- 本人に面接したり、状況を調査したりします。
- 親族へ意向を問い合わせます。
- 必要に応じて医師による鑑定が行われます。
- 審判成年後見人等が決まります。
本人や成年後見人等に通知されます。
※この間に法定後見の開始の審判に異議申立てができます。
即時抗告 2週間 - 審判確定東京法務局に登記されます。
- 成年後見人等の活動開始成年後見人等は定期的に家庭裁判所ヘ後見事務の報告を行い、監督を受けます。
- 本人の死亡
- 成年後見人等の辞任
- 成年後見人等の解任
- 本人の能力回復による成年後見等の審判の取り消し
- 成年後見人等の活動終了
申立て及び審判手続に必要なもの
| 申立て及び審判手続に必要なもの | 入手先など |
|---|---|
| 申立書・申立事情説明書・財産目録 等
※その他家庭裁判所から必要書類の提出を求められる場合あり |
|
| 申立て手数料(800円の収入印紙) | 郵便局・法務局等 |
| 登記手数料(2,600円の収入印紙) | 郵便局・法務局等 |
| 郵便切手(後見4,000円分、保佐・補助5,000円分)
※裁判所が送達・送付費用として使用 |
郵便局等 |
| 本人の戸籍謄本 1通 住民票 1通(マイナンバーの記載のないもの)※住民票は戸籍附票でも可 |
本人の本籍地の市区町村 本人の住民登録地の市区町村 (本人の本籍地の市区町村) |
| 成年後見人等候補者の住民票 1通
※住民票は戸籍附票でも可 |
候補者の住民登録地の市区町村 |
| 本人の登記されていないことの証明書 1通 300円(収入印紙) |
|
| 本人情報シートのコピー | 福祉関係者に依頼します。 |
| 診断書および鑑定についての照会書 | 申立人が医師に依頼します。 診断書の様式は申立て書類の中にあります。 |
| 本人の健康状態に関する資料 (例:介護保険認定書、療育手帳(愛の手帳)などのコピー) |
お持ちでない方は、区役所高齢・障害支援課へお問い合わせください。 |
| 鑑定書(後見、保佐の場合原則必要、鑑定料は、5~10万円程度のようです。) | 家庭裁判所が選任する鑑定人に依頼します。 |
※申立て費用は原則申立人負担
区長による申立て
身寄りがない、身内から虐待を受けている、親族が協力しないなどの理由で申立てをする人がいない方の保護を図るため、市町村長(横浜市では区長)も法定後見の申立てができます。
詳しくは、各区役所高齢・障害支援課にお問い合わせください。
成年後見制度利用支援事業
成年後見の申立て費用や後見人等への報酬の負担が困難な方には、その費用の全部又はー部の助成があります。ただし、申立て費用については、区長が申立てを行った人を対象としています。
詳しくは、各区役所高齢・障害支援課へお問い合わせください。